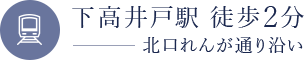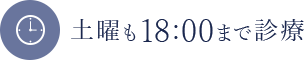椎骨動脈解離と脳卒中のリスク
下高井戸脳神経外科クリニック院長の髙橋です。
今回は、脳の血管に関わる重要な病気のひとつ「椎骨動脈解離(ついこつどうみゃくかいり)」についてお話し致します。
頭痛と脳の血管の病気
頭痛には大きく分けて2つの種類があります。
ひとつは二次性頭痛と呼ばれるもので、他の病気の結果として起こる頭痛です。もうひとつは片頭痛や緊張型頭痛のように、それ自体が治療対象となる一次性頭痛です。
二次性頭痛の中には、くも膜下出血のように血管が破れて急速に悪化する危険な病気も含まれます。そのため脳神経外科医は、問診・診察・画像検査を組み合わせて「血管のトラブルによる頭痛かどうか」を常に念入りに確認します。
特に注意が必要な頭痛は以下のようなものです。
-
・今までに経験したことのないような強い痛み
-
・突然始まり、何時何分に始まったとはっきり分かるような頭痛
-
・頭痛に加えて、意識消失、しゃべりにくさ、めまい、手足のしびれや動かしにくさなどを伴う場合
もちろん、これらに当てはまらなくてもそれだけでは安心はできません。問診で詳しい状況を伺い、神経学的な診察を行い(目の動きをみたり髄膜の刺激症状を診たりします)、さらにMRIやMRAで出血がないことや血管の形を確認することによって、危険な頭痛を慎重に除外していきます。
椎骨動脈解離とは?
患者さんが「後頭部や首筋の一か所が突然強く痛んで、それからずっと頭痛が続く。これまでにこんなことはなかった」とおっしゃる場合、椎骨動脈解離を鑑別診断の一つとして診察を進めます。実際に椎骨動脈解離の患者さんの60%以上が、突然の激しい首の痛みや頭痛を経験すると報告されています。
椎骨動脈解離は、首から脳へ血液を送る椎骨動脈の壁に亀裂が入り、血液が壁の間に流れ込んでしまう病気です。
大きく分けて「自然発生性」と「外傷性」があり、原因が特定できない「特発性」のものもあります。
-
自然発生性
軽い首の動き(回す、伸ばすなど)がきっかけになったり、高血圧、片頭痛の既往、結合組織疾患、遺伝的素因が関与します。「高い枕」を使う習慣がリスクとなることも報告されていて、「Shogun pillow syndrome(将軍枕症候群)」と名前がつけられています。 -
外傷性
スポーツや交通事故の衝撃、ヨガや柔道、あるいはカイロプラクティックなどの過度な首の動きが原因となることがあります。
椎骨動脈解離の症状と病態
椎骨動脈解離は、頭痛だけで経過することもあれば、脳梗塞やくも膜下出血を引き起こすこともあります。
-
頭痛や首の痛み
椎骨動脈解離の発症時に頭痛のみを訴える割合は、研究によって55%から62%程度と報告されています。頭痛のみで経過する場合は、頭痛自体も時間とともに改善し、比較的予後も良好です。 -
脳梗塞
多くの患者さんは数時間から数日以内に小脳や延髄に梗塞を起こし、めまい、ふらつき、言語障害、嚥下障害などを生じます。もっと時間が経過してから脳梗塞を起こすこともあります。 -
くも膜下出血
特に頭蓋内で解離が起きた場合、外膜が破れてくも膜下出血を起こすことがあります。これは命に関わることも多く、予後が悪化します。
発症直後の数日から4週間は脳梗塞のリスクが最も高く、出血に関しては解離の発症直後に多いとされています。そのため早期の診断・対応が重要です。
診断と検査
椎骨動脈解離の診断にはMRI・MRAが中心となります。
-
MRA(TOF法):血管内の血流の様子から血管の狭窄や閉塞、拡張を評価
-
BPAS:血管外径の変化を評価、膨らみがあれば出血リスクに注意
-
T1強調画像 thin slice:血管壁内の血栓を描出し、発症時期の推定に有用
当院ではこれらすべての撮影法が可能です。
治療と経過観察
-
脳梗塞がある場合
抗血小板薬や抗凝固薬による治療が選択されますが、出血リスクもあるため慎重に行います。 -
くも膜下出血がある場合
再出血を防ぐため、血管を閉塞するコイル塞栓術やトラッピング術が行われます。条件によってはバイパス術が必要となることもあります。 -
経過観察
脳梗塞も脳出血も起こさずに、頭痛のみ、もしくは検査で偶然に見つかった場合には経過観察が選択されることもあります。こまめにMRI等で血管の形態および脳梗塞、脳出血の有無を確認、必要がある場合には血圧をコントロールし、頸部に負担がかからないような生活習慣をお願いします。
椎骨動脈解離後のフォローアップ
前述のように、椎骨動脈解離の結果として生じる「解離性椎骨動脈瘤(血管の膨らみ)」は、発症から2週間を超えると出血の可能性は低くなると考えられています。しかし慢性期に出血することもあり、その際の予後は不良であるため慎重なフォローが必要です。
また、発症から1か月程度の間は、驚くほど血管形態が変化することがあります。これは「リモデリング」と呼ばれ、血管の太さが元通りに治ることさえあります。一方で、発症3〜6か月を過ぎても形態異常が残る場合は、そのまま永続化することが多いです。
発症早期は血管が目まぐるしく変化し、場合によっては重篤な脳梗塞を引き起こす危険があるため、1週間ごとなど短い間隔で画像検査を繰り返し、血管形態の変化が落ち着くまで丁寧に経過観察することが安全と考えられています。
日常生活での注意点
椎骨動脈解離のフォローアップには、以下の点が大切です。
-
・過度な首の動きや衝撃を避ける(1〜6か月は特に注意)
-
・高枕の使用を避ける
-
・禁煙、血圧や脂質の管理など生活習慣の改善
-
・降圧薬などの処方(必要時)
-
・めまい・視覚異常・手足の脱力などの症状があればすぐに受診する
-
・定期的にMRI・MRAでフォローアップを行う
まとめ
椎骨動脈解離は若い方にも発症しうる脳血管の病気であり、頭痛や首の痛みから始まり、脳梗塞やくも膜下出血といった重篤な状態に進展することもあります。
適切な診断と治療、そして日常生活での注意を守ることで、予後を改善できる可能性がある病気です。
「今までにない強い頭痛」や「首筋の突然の痛み」がある場合は、脳神経外科を受診をご検討ください。