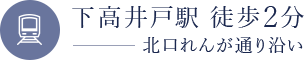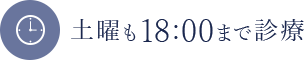頭痛―片頭痛の急性期治療と予防的アプローチ
下高井戸脳神経外科クリニック院長の髙橋里史です。今回は頭痛、特に片頭痛についてお話しさせて頂きます。
頭痛は現代人に多い疾患―我慢は禁物です
頭痛は非常に身近な症状で、多くの人が日常的に悩まされています。片頭痛と緊張型頭痛という2大頭痛に限っても、日本人の約3~4人に1人が「頭痛持ち」と推定されています。ある年に、その病気を持っていた人の割合である年間有病率は片頭痛で8.4%、緊張型頭痛で22.3~22.4%とされています。
特に片頭痛の好発年齢のピークは男女ともに働く世代に一致するため、片頭痛が社会全体の生産性に及ぼす影響は大きく、日本では片頭痛により年間3,600億円~2兆3,000億円の経済的損失が推計されています。これは頭痛が酷く仕事にいけないという欠勤(アブセンティーイズム)による損失に加え、出勤していても頭痛で仕事の能率が著しく低下する状態であるプレゼンティーイズムの影響も深刻であることが背景にあります。
それにもかかわらず、「頭痛は医学的に治療すべき疾患」という認識は依然として十分ではなく、約7割の方が「いつもの頭痛だから」と受診せずに我慢してしまうという報告もあります。その結果、必要な診断や治療が遅れ、頭痛によりQOL(生活の質)が長期にわたり損なわれてしまいます。

まずは「危険な頭痛(二次性頭痛)」を見逃さない
頭痛は大きく頭痛自体が治療対象である一次性頭痛と、頭の中の疾患が原因で頭痛が起こる二次性頭痛に分類されます。
特に雷鳴頭痛と呼ばれる「突然発症し、1分未満で最大強度に達する激しい頭痛」や、「手足の動かしにくさやしゃべりづらさ、意識消失を伴う”いつもと違う”頭痛」は重篤な脳疾患のサインの可能性があります。このような症状では、くも膜下出血/可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS)/下垂体卒中などを念頭に問診、診察、MRI検査を行います。
一次性頭痛の代表と特徴
危険な頭痛を除外した後は、国際頭痛分類であるICHD-3に沿って一次性頭痛を同定します。以下に代表的な一次性頭痛を挙げます。
• 片頭痛:中等度~重度の拍動性の痛み。悪心・嘔吐、光過敏、音過敏を伴いやすい。静かな暗い部屋でじっとしていたくなるような痛みです。
• 緊張型頭痛:頭全体の鈍い痛み・圧迫感。姿勢・眼精疲労・ストレスで悪化。頸椎の並び方が影響する場合があります。“孫悟空の輪っかで絞められているよう”と表現される頭痛です
• 後頭神経痛:後頭部や耳介後部の差し込むような短い痛み。神経の走行上に圧痛を認めます。
• その他にも群発頭痛、一次性咳嗽性頭痛、一次性運動時頭痛、一次性穿刺様頭痛、睡眠時頭痛などがあります。
片頭痛の負担:WHO/GBDの正しい理解
数ある一次性頭痛の中でも最も生活に影響を与えている頭痛が片頭痛です。世界保健機関(WHO)は、世界の疾病負担に関する研究(Global Burden of Disease:GBD)において、片頭痛を「障害生存年数(Years Lived with Disability:YLD)が増加する疾患の第2位」に位置づけています。
YLDとは、日常生活への障害負担を数値化して、存命中の疾病負担を表した指標です。すなわち、片頭痛は日常生活への負担が極めて大きい疾患であることが、国際的なコンセンサスとなっているのです。
誘因の理解①:環境・天候・気圧の変化と片頭痛
環境の変化は片頭痛の重要な誘因です。88%超の患者さんが環境の変化を片頭痛の誘因として挙げています。関連する環境の変化としては精神的ストレス、疲労、睡眠不足等が挙げられ、片頭痛に特異的な誘因群と考えられています。
また、低気圧で頭痛が誘発されたり、増悪したりする方が少なくありません。漢方薬である五苓散(ごれいさん)は、アクアポリンという細胞膜の水の通り道(チャネル)を介した水分調整を行い、「低気圧の時に起こりやすい頭痛」に対して使用されることがあります。
対処の基本
• 兆候が強まる前から規則正しい生活を意識(起床・食事・就寝リズムの安定)。
• 睡眠時間の確保、こまめな気分転換、適度な運動。
• 脱水・空腹を避ける(朝食抜き・偏食を減らす)。
• 気圧変化が苦手な方は、天気アプリ等で予測し先回りの対策(休息計画、頓用薬の準備、必要に応じて五苓散の内服を検討など)。
誘因の理解②:光と体内時計―片頭痛の患者さんが「朝日を浴びること」の意義
人の体内時計は約25時間のリズムを持つとされ、毎朝の“リセット”が重要です。とくに
1) 明るい光(太陽光)を浴びる、2) 発声(挨拶)、3) 朝食
の3要素が体内時計を24時間周期に同調させることに有効であるとされています。朝の強い光はサーカディアンリズムを朝型へ切り替える合図として働き、睡眠の質・日中の覚醒度・片頭痛の起こしにくさにも好影響が期待できます。
一方で、片頭痛発作の数時間前である予兆期には光過敏が現れやすく、発作中は明るい光が誘発・増悪因子になりえます。したがって、
• 平常時:起床直後の適切な朝日で体内時計を整える(室内でもカーテンを開ける/必要に応じて明るい照明)。
• 予兆期・発作時:遮光(サングラス・キャップ・遮光カーテン)や静かな環境で光刺激を減らす。
という、ケースバイケースの対応が重要になります。長すぎる昼寝(午睡)は時差(ジェットラグ)様の体内時計のズレを招き、眠気・頭痛・倦怠感を増悪させうるため昼寝は短時間(15–20分程度)にとどめるのが安全です。
誘因の理解③:食事・飲料と生活リズム
• アルコール(とくにワイン=アルコール+ポリフェノール)は血管拡張を介して片頭痛を誘発しやすいことが知られています。
• チョコレート、チーズ、人工甘味料等の特定の食品には誘発報告があります。ご自身の片頭痛のパターンを把握して摂取の調整が必要になります。
• グルテン感受性(小麦などに含まれるたんぱく質である「グルテン」を摂取することで、身体的・精神的症状(腹痛、下痢、頭痛、倦怠感、抑うつ、不安など)が引き起こされる状態や症候群)が疑われる場合、パン・パスタなど主食の見直しも選択肢となります。
• 欠食(朝食抜き・偏食)や空腹は片頭痛の誘発因子です。規則正しい食事で血糖変動を緩やかにすることが推奨されます。
• カフェインは急性期治療の補助になり得る一方、過量や連用(概ね200 mg/日(インスタントコーヒー2.3杯分)超)は片頭痛を誘発する可能性があるため注意が必要です。
• 水分:脱水は片頭痛の誘発リスクになります。こまめに水分を摂取して下さい。
片頭痛の病態生理:最新の理解(このセクションは専門的な話になりますので、ご興味のある方だけお読み下さい)
1) 三叉神経血管説
発作時、脳を包む膜である硬膜の血管周囲にある知覚神経である三叉神経の終末が活性化し、CGRP/VIP/NOなどの物質が放出されます。これらが血管拡張と神経原性炎症を誘起し、入力が頸髄・三叉神経複合体(TNC)→視床→帯状回・島皮質などペインマトリックスへ伝達され、拍動性頭痛として知覚されます。また、自律神経核への投射で悪心・嘔吐等が生じます。
2) CGRPの中心的役割
CGRPは三叉神経の一次ニューロンに豊富で、発作時に放出され血管拡張/痛覚過敏/炎症メディエーターの増加をもたらします。CGRP機能の阻害で発作が治まり・また発作が予防されることから、CGRP関連抗体薬(ガルカネズマブ/フレマネズマブ/エレヌマブ)が予防治療として登場しました。
3) 皮質拡延性抑制(CSD)
片頭痛発作前兆の生理学的基盤。皮質で生じる脱分極と活動抑制が2~5 mm/分で伝播し、局所の細胞外K⁺やCGRP上昇を介して硬膜の三叉神経を刺激し、頭痛を誘発します。視覚前兆では後頭葉に沿って閃輝暗点が約3 mm/分で移動する報告があります。睡眠不足やエストロゲンで感受性は高まり、バルプロ酸などの予防薬で低下します。
治療①:急性期治療(頓用薬)—「早く・適量・適剤形」
目標は「2時間以内の頭痛消失と日常活動の回復」。
• NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬):いわゆる一般的な痛み止めです。COXという酵素を阻害することでプロスタグランジンの産生を抑制することで炎症と痛みを鎮めます。軽度発作で有用ですが、中等度以上では限界があります。
• トリプタン製剤:片頭痛に特異的に効果を発揮します。セロトニン(5-HT1B/1D)受容体に作用し、脳血管収縮・CGRP放出抑制・神経原性炎症の抑制を介して病態へ根本的に介入します。片頭痛の第一選択とされ、頭痛出現後できるだけ早期の使用が重要です(前兆の最中ではなく、前兆が終わり痛みが始まったら直ちに)。
• 剤形の選択:錠剤/点鼻薬/皮下注射薬。
→起床時や夜間に痛みで目が覚めた、悪心・嘔吐が強いなど内服が遅れやすい場面では、非経口製剤(点鼻・皮下注射)が推奨されます。
→皮下注射薬は最も速効(投与後約10分で発現)かつ高い有効性(頭痛消失率60~80%)が示され、錠剤無効でも点鼻・注射で反応する例があります。
• 制吐薬:悪心・嘔吐が強いと内服遅延・吸収不良を招くため、適宜併用します。
薬剤使用過多による頭痛(MOH)に注意
片頭痛の既往があり、3か月超にわたり
• トリプタン/エルゴタミン等:月10日以上
• 単純鎮痛薬:月15日以上
使用するとMOHに該当。原因薬の中止、急性期対処、予防薬が治療原則です。
治療②:予防療法(片頭痛が「起きにくい」状態に)
適応の目安:月2回以上の発作、あるいは生活に支障をきたす頭痛が月3日以上、MOHリスクが高い場合などで検討されます。①の急性期頓用薬でのコントロールが困難な際に検討します。
• 従来薬:ロメリジン(Ca拮抗薬)/バルプロ酸(抗てんかん薬)/プロプラノロール(β遮断薬)があります。それぞれメリット、デメリットがあり、医学的背景を勘案し薬を決めていきます。
• 新規薬:CGRP関連抗体薬(ガルカネズマブ/フレマネズマブ/エレヌマブ)—有効性・安全性に優れ、QOL改善が期待されます。
• 生活介入:良質な睡眠・規則正しい食事・適度な運動・ストレスコーピング・補水が有効です。誘因の過度な厳格回避はストレス増で逆効果になるので避けるべきとの意見もあります。「ご自身の片頭痛の誘因パターン」の見える化とテイラーメードの対処法の確立が鍵となります。
おわりに
頭痛には何か原因が隠れていることがあります。また、頭痛自体が治療対象である一次性頭痛は日常生活の質を大きく損ないます。仕事や子育て、家族や友人との時間を楽しみたいのに「頭痛があるせいで…」と我慢されている方も多いのではないでしょうか。
「頭痛さえなければ、もっと自分らしく過ごせるのに」――その思いに寄り添います。
杉並区・世田谷区エリア、京王線・世田谷線沿線の脳神経外科頭痛外来として、当院ではMRIを活用した診断と個々人に対するテイラーメード片頭痛治療を提供しています。いつもの頭痛だからと我慢してしまう前に、是非一度ご相談ください。
ご予約はWebから24時間受け付けています
外来のご予約はこちら(杉並区・下高井戸)
よくあるご質問(Q&A)
Q. アルコールはダメですか?
A. 個人差はありますが、ワイン(アルコール+ポリフェノール)などは誘発因子として報告されています。ご自身の誘因パターンを記録し、量や頻度を調整することが大切です。
Q. 朝日は浴びた方がいい?
A. 平常時は推奨されます。体内時計をリセットする効果があり、生活リズムの安定に役立ちます。一方で、片頭痛の予兆期や発作中は光過敏が強くなるため、遮光(サングラス・カーテンなど)で光を避けることが大切です。長い昼寝は体内時計を乱すため避けましょう。
Q. 起床時の激しい発作は?
A. 内服が遅れやすいため、点鼻薬や皮下注射薬といった非経口のトリプタン製剤が有用です。特に皮下注射薬は10分ほどで効果が出現し、頭痛消失率も高いとされています。早期投与が鍵です。予防的視点からは睡眠不足を避け、起床直後に「光・発声・朝食」で体内時計を整えましょう。長い昼寝は避け、気圧による誘発が明らかな場合は漢方薬の使用が選択肢になります。
Q. 小児・思春期でも片頭痛はおきますか?
A. はい。成人とは異なり、持続時間が短い/両側性が多い/後頭部痛はまれといった特徴があります。まず二次性頭痛の除外が大前提です。
基本は非薬物療法
「小児・思春期の片頭痛は、患者教育を含めた非薬物療法を前提に取り組むことが推奨」されています。
推奨される生活習慣
• 睡眠衛生(就寝・起床時刻を一定に/スクリーンタイム制限/寝室環境の整備)
• 規則正しい食事(朝食を抜かない/脱水を避ける)
• 適度な運動(軽中等度の有酸素運動)
• ストレス対策
• 保護者の関与
• 栄養補助:ビタミンB2、マグネシウム、CoQ10、メラトニンなど
薬物療法(必要な場合)
• 急性期:イブプロフェン(第一選択)、アセトアミノフェン。NSAIDsが不十分なら年齢に応じたトリプタンを考慮します。
Q. 片頭痛は治りますか?
A. 「完治」ではなく「コントロールして上手に付き合う」病気です。加齢に伴い発作が減る方もいらっしゃり、高齢になると発作は減り前兆だけが残るケースもあります。
Q. 妊娠中の片頭痛の対応は?
A. 妊娠中は多くの場合片頭痛が軽快傾向(60~80%)となり、特に前兆のない片頭痛では改善が目立ちます。妊娠後期になるほど発作が減る一方、出産後1か月以内に再発しやすいことが知られています。
• ホルモンの安定(エストロゲン・プロゲステロン)が軽快に寄与すると考えられています。
• 授乳の継続は再発を抑制する可能性があります。
• NSAIDsは妊娠後期は禁止。
• 妊娠中のトリプタンは安全性未確立です。
• 妊娠中の予防薬の使用は原則避け、非薬物療法(生活指導・行動療法・理学療法など)が中心となります。
Q. 診察費はいくらかかりますか?
A. 二次性頭痛の除外やトリプタン投与前の禁忌事項(脳血管障害)確認のためMRI・MRAをお勧めしています。
• MRI費用(保険診療3割負担):約6,000円(MRAを追加しても同額です)
• 初診時合計:約10,000円前後(保険診療3割負担)(診察料・検査料含む)
• 再診+処方のみ:保険診療3割負担で概ね1,000円以内(薬代は薬局にて別途必要)
いつもの頭痛で、既に他院でMRIを実施し異常なしと確認済みの場合、必ずしも当院で再度MRIを行って頂く必要はありません。