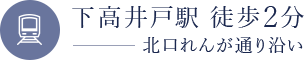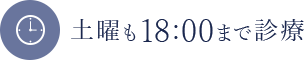内装完成と当院のロゴについて
内装完成のご報告
下高井戸脳神経外科クリニック院長の髙橋里史です。2025年8月22日、本日クリニックの内装のお引き渡しをいただきました。
内装をお引き受けくださった ウェルハートの木村様、杉本様、佐藤様をはじめご関係のみなさま に心より感謝申し上げます。
完成した空間は、想像をはるかに超える仕上がりでした。ウェルハート様が掲げる「美しいクリニック」という理念と、私自身の「落ち着ける森をイメージしたクリニック」という希望を、ウェルハート様の手腕で見事にひとつに融合していただきました。
一見すると高級感のある雰囲気ですが、当院は保険診療を中心とした地域のためのクリニックです。もちろん一部、自費による脳ドックなども行いますが、日常の診療を支える場として、どなたさまも安心してご来院いただければ幸いです。

① クリニックの内装コンセプト ― 森
人が安らぎを感じる自然は、それぞれ違うと思います。山や海、川、桜や雪景色など…。
私が一番安らぎを感じる自然は 森 です。
10歳のころに過ごした、西ドイツ・マールブルクという街での記憶が大きく影響しているのだと思います。マールブルクは旧市街地自体が森に囲まれた中世の街で、私が当時住んでいた郊外の森の中で友人たちと木製遊具を駆け回った体験は、今でも心に残っています。
系譜をたどればライン川の東から東ヨーロッパまで広がる古代ヨーロッパの広大な森林地帯の一部で、かつて古代ローマ人が恐れた「ヘルキニアの森」、カエサルが著した『ガリア戦記』に登場する森でもあります。とはいえ実際は、不気味さではなく深い安らぎを与えてくれる空間でした。
森はまた、ソローが『ウォールデン 森の生活』で「本当の幸福とは何か」「どう生きるべきか」と内省した場所でもあります。さらに緑色には、片頭痛を和らげる効果があるとも言われています。
ご来院の皆さまが少しでも落ち着きを取り戻せるように。そんな願いを込めて、このクリニックは「森」をコンセプトとしました。

② ロゴに込めた想い ― 共生と進化
当院のロゴは、私がまずイメージを描き、デザイナーさんに形にしていただき、その後さらに調整を重ねて完成しました。
背景にあるのは、建築家・黒川紀章氏の思想です。
当時できたばかりの国立新美術館に偶然立ち寄り、そこで出会った「黒川紀章展」で、氏の都市構想に強い衝撃を受けました。なかでも「東京計画1961(Helix City)」に示された「都市と海(水)」の新しい関係づけは圧巻で、そこから黒川氏の「共生の思想」に出会いました。
この「共生の思想」は、対立する二つの要素をどちらかに寄せるのではなく、両方を活かして新しい関係を築くという考え方です。
![]()
ロゴの形と意味
ロゴは 二つの螺旋が絡み合い、全体として脳を象徴 しています。
螺旋は「S」の字を描いており、
-
Support(サポート):患者さまを支える姿勢
-
Shimotakaido(下高井戸):地域に根ざす場所
を同時に表しています。
また、螺旋は「変化」と「進化」を象徴し、常に成長し続けるクリニックの姿勢を表現しています。流れるようなラインは「調和」や「柔らかさ」を加え、共生の思想を視覚的に示しています。
ロゴカラーの意味
-
ネイビーブルー
深い青は 安心・誠実・知性 を象徴。
地域に根ざした日常診療や、患者さまとの信頼関係を大切にする姿勢を表しています。 -
ゴールドオーカー
温かな黄金色は 革新・希望・前進 を象徴。
AI搭載MRIなどの先端技術を積極的に導入し、未病段階からの予防医療を目指す姿勢を示しています。
この二色は、また対立する概念を超えて調和する「共生の思想」を体現しています。
「共生の思想」で解釈するホスピタリティと医療DX
当院が大切にしているのは、「人の力」×「機械の力」 という考え方です。
よくある二元論として、
-
「医療は人が全て。機械は冷たくて温かみがない」
-
「人の作業は非効率。DXで全て自動化すべき」
といった両極端の主張があります。これはまさに「人間 vs 技術」「伝統 vs 最新」という対立構造そのものです。
しかし共生の思想に立つと、どちらかを否定するのではなく、両方を活かす道 を探すことができます。
その答えのひとつが、テクノロジーによって再設計された 「新しい患者体験(ペイシェント・ジャーニー)」 です。
受付や予約の効率化はDXが担い、診療の中での安心感や寄り添いはスタッフのホスピタリティが支える。両者が共に働くことで、患者さまにとってより快適で安心できる体験が生まれます。
「共生の思想」で解釈する未病と疾病
また、黒川氏の「共生の思想」の核心は、西洋的な二元論(AかBか)を乗り越え、対立する要素をそのまま内包し、中間領域を設けることで新しい関係性を築くことにあるのではないかと考えています。
このフレームワークを使って、「健康」と「病気」の関係を再解釈してみます。
1. 乗り越えるべき二元論:「健康」 vs 「疾病」
現代の一般的な健康観は、黒川氏が批判した「機械の時代」の二元論に似ています。
-
二元論的モデル:人は「健康である」か「疾病である」かのどちらか。
-
境界線:検査数値や症状の有無によって、健康と病気の間に線が引かれる。
-
捉え方:体を「正常に作動する機械」か「故障した機械」として見る発想。
この「0か100か」の考え方こそ、乗り越えるべき二元論です。
2. 中間領域としての「未病」
ここでの 「未病」 は、まさに黒川氏が重視した「中間領域」そのものではないでしょうか。
-
未病の状態:健康とは言えないが、疾病とも診断されない。両者に属さない曖昧でグラデーションのある状態。
-
役割:この「未病」にフォーカスすることで、「健康か、病気か」という単純な二項対立から抜け出すことができます。体は常に揺れ動く存在であり、白黒つけられない状態こそ生命の本質だという視点につながります。
◆ 日常診療での「未病」の具体例
-
検査の数値が少しだけ基準を超えている場合
まだ「病気」と診断されるほどではないけれど、将来的に動脈硬化や脳梗塞につながるリスクがある状態です。この段階で生活習慣を整えることが、病気を防ぐ第一歩となります。 -
頭痛やめまいが「病気」と言い切れない場合
片頭痛や自律神経の乱れなど、検査で大きな異常は見つからなくても、生活の質を下げる症状があります。こうした場合も「未病」の一部と捉え、薬物治療だけでなく生活アドバイスやストレス管理を提案します。 -
診察時の声かけ
「異常はありませんでした」で終わらせるのではなく、数値や症状の背景にある生活習慣を一緒に見直す。それによって、患者さまが“病気になる前の揺らぎ”に気づき、早めに対策を取ることができます。 -
未破裂脳動脈瘤
発見されても無症状であることが多い状態です。しかし放置すればくも膜下出血につながるリスクがあります。未破裂脳動脈瘤を「未病」と捉え、血圧などのリスク因子を管理することで、くも膜下出血のリスクを下げる 先制医療 を実践します。 -
頸動脈狭窄
脳梗塞を起こす前の段階では「未病」と位置づけられます。血管の狭窄を早期に見つけて治療することで、脳梗塞の発症リスクを下げることができます。これもまた 先制医療 の重要な柱と考えています。
クリニックが目指すもの
当院は、
-
スタッフによる温かなホスピタリティ と 医療DXによる効率化・精度 の両立
-
健康と疾病の間にある「未病」へのアプローチ
を大切にしていきます。
ロゴに込めた願いは、
「患者さま一人ひとりの“これから”を支える存在でありたい」 ということ。
治療と予防、伝統と先端、日常と医療。
その間に橋をかけるクリニックとして、地域の皆さまと共に歩んでまいります。
📍2025年9月17日 新規開院
頭痛やめまいなど、お困りの症状がありましたらご相談ください。