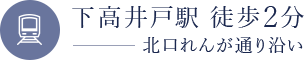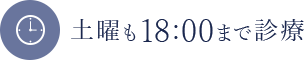動脈硬化と脳卒中の関係
① 動脈硬化とは何か
動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールや中性脂肪といった脂質が沈着し、血管の壁が厚く硬くなることで、血液の通り道が狭くなってしまう状態を指します。
血管は本来、しなやかで弾力があり、心臓の拍動に合わせて伸び縮みしながら血液を全身に送り出しています。しかし、動脈硬化が進むとこの弾力が失われ、血管がまるで硬いパイプのようになってしまいます。実際、動脈硬化を起こしている血管は黄色く見え、触るとカチカチの管のような感触であるのに対し、健康な血管は赤く柔らかく、押すと弾力性があり反発してくるという違いがあります。
動脈硬化は年齢とともに誰にでも少しずつ進む“血管の老化現象”ですが、その進み具合は生活習慣や基礎疾患によって大きく変わります。特に、高血圧・脂質異常症・糖尿病・肥満・喫煙・過度の飲酒・運動不足・ストレスといった条件が揃うと、血管はどんどん傷つき、動脈硬化が急速に進行していきます。
② 動脈硬化が脳に及ぼす影響
脳は血液を常に必要とする臓器です。また穿通枝と呼ばれる血管で栄養される脳の部分は、その穿通枝が詰まってしまうと他から血流を受けることが出来ず、直ちに脳梗塞を来し症状として現れます。脳の細い動脈自体に動脈硬化が起こると、血液が流れにくくなり、最終的には血管が詰まることで引き起こされる脳梗塞をラクナ梗塞といいます。ラクナ梗塞を起こすと、突然手足の麻痺が生じたり、言葉が出づらくなったり、話しにくくなったり、様々な神経症状が出現することがある一方、比較的小さいラクナ梗塞が目立った機能を持たない脳の部分に生じることがあります。正確な医学用語ではありませんが、いわゆる隠れ脳梗塞です。
はっきりとした症状がないまま細かい梗塞(ラクナ梗塞)を繰り返しているケースも少なくなく、気づかないうちに脳の神経細胞がじわじわと傷ついていくことで記憶力・判断力の低下(血管性認知症)につながることもあります。つまり動脈硬化は、脳梗塞だけでなく「脳の老化」を早める大きな要因でもあるのです。
また頚動脈や大動脈等、より心臓に近い太い血管にも動脈硬化性の変化が生じます。特に頚動脈分岐部や大動脈弓部は動脈硬化の好発部位で、この部分で生じた血栓が原因でラクナ梗塞より広い範囲に脳梗塞を生じるのがアテローム血栓性脳梗塞です。
③ 動脈硬化の評価(MRIと採血)
脳の動脈硬化の進行度を調べる方法として、MRI等の画像検査と採血検査があります。
MRIでは、脳主幹動脈と呼ばれる比較的太い脳血管の狭窄(細くなっている部分)や、過去に脳実質に無症状で起きた小さな脳梗塞の跡、症状を起こさないまま経過した小さな脳出血の跡(微小出血)を見つけることができます。MRIでは頸動脈に生じたプラークの脆弱性も評価することができ(プラークイメージと言います)、将来の脳梗塞リスクを推定し、リスク低下のための適切な医学的方針を立てる一助となります。
一方、採血では、総コレステロール値、LDL(いわゆる悪玉)コレステロール、HDL(いわゆる善玉)コレステロール、中性脂肪、血糖値、HbA1cなどを測定します。これらは動脈硬化を進める“背景因子”となるものであり、数値が高いまま放置すると血管の動脈硬化が進んでいく可能性が高くなります。画像と採血の両面から評価することで、その方の「現在の脳主幹動脈および脳の状態」と「動脈硬化を助長するリスク因子」を客観的に把握することができるのです。
④ 動脈硬化を予防するために(生活習慣・投薬)
動脈硬化を予防する第一歩は、毎日の生活習慣を整えることです。
- 食事:脂分の多い食事や塩分・糖分のとりすぎを控え、野菜・魚・海藻・大豆製品などを中心とした和食やオリーブオイルが主役で全粒穀物と魚介類を積極的に摂取する地中海食を意識する
- 運動:ウォーキングなどの軽めの有酸素運動を1日30分程度、週3〜4回継続する
- 禁煙・節酒:喫煙は血管を直接痛めるために止める。飲酒は高血圧や脂質異常を招くことがあるため摂取量に注意する
- 適正体重の維持:肥満を改善することで血管への負担を軽減する
なかでも重要なのが血圧コントロールです。高血圧の状態が続くと、血管は常に高い圧力にさらされて傷つき、そこにコレステロールが付着しやすくなって動脈硬化が進行します。「上の血圧が140mmHg以上」「下が90mmHg以上」の状態が続く方は、食事の減塩や運動に加え、必要に応じて降圧薬による治療開始のご相談をさせて頂きます。
生活習慣の見直しだけでは十分な効果が得られない場合には、スタチンやEPA等の脂質異常症治療薬、高血圧治療薬(降圧薬)、糖尿病治療薬、血液をサラサラにする抗血小板薬の中から、必要な薬物を選び併用します。生活習慣と薬物治療を両立することで、動脈硬化の進行を抑え、脳梗塞の発症を効果的に防ぐことが可能です。ちなみに抗血小板薬は脳梗塞リスクを下げる一方、同じ動脈硬化が助長する脳出血のリスクを上げます。①不要な抗血小板薬の投与は避ける②病態に合った抗血小板薬と量を考える③抗血小板薬開始後に適切な血圧コントロールを行う、ことが重要であると考えています。
⑤ 下高井戸脳神経外科クリニックでできること(京王線・東急世田谷線 下高井戸駅/脳MRI)
当クリニックでは、頭部MRI/MRAや頸動脈MRAおよびプラークイメージ等の検査を用いた画像による血管の評価、および採血による生活習慣病リスクのチェックを日常的に行うことで、無症状のうちから「血管の老化」に気づくことができる体制を整えています。
高血圧・脂質異常症・糖尿病などすでに治療中の方には、主治医の先生や近隣クリニックの先生方と連携しながら、脳卒中の発症・再発を防ぐための専門的なフォローアップも提供して参ります。また、検査結果をもとにした生活習慣の改善アドバイスも行います。
「症状が出てから」ではなく、未病の段階で動脈硬化を発見し「症状が出る前」に先制医療を行い備えること——それこそが脳梗塞、脳出血等の脳卒中予防の最も大切なポイントです。
動脈硬化は自覚症状なく静かに進行する“サイレントキラー”です。「健診で高脂血症を指摘された」「家族が脳梗塞で心配」「最近なんとなく物忘れが増えた気がする」――そんな小さなきっかけからで構いません。京王線沿線、世田谷区・杉並区で頭部MRIによる検査をご検討中の方は、お気軽に下高井戸脳神経外科クリニックまでご相談ください。