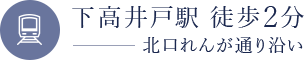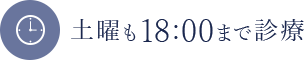微小出血
微小出血~MRIでわかる所見
「脳の微小出血(Cerebral microbleeds: CMBs)」とは、ごく小さな血管からにじむように出た出血の跡を示す所見です。
通常のMRIでは見えにくいのですが、T2*強調画像という特殊な撮像法を使うと検出することができます。
ここでは、①MRIでの見え方、②医学的な意味、③見つかったときの対応について、専門的な内容を保ちつつわかりやすくまとめます。
① MRI(T2*強調画像)での「微小出血」の見え方
どのように見えるか
T2*強調画像では、微小出血は小さな黒い点(低信号)として映ります。形は丸いか楕円形で、直径は1cm未満です。
これは、過去の出血の跡に残るヘモジデリンという鉄を含む色素がMRIの磁場を乱すため、黒く抜けて(信号が消えて)見えるからです。
なぜT2*強調画像でわかるのか
ヘモジデリンなどの常磁性物質は磁場の影響を受けやすく、T2*強調画像では強く反応します。
そのため、直径0.2mm以下の細い血管からのにじみでも検出できる高感度な撮像法です。
黒い影が実際より大きく見える理由
「ブルーミング効果」と呼ばれる現象で、実際の出血よりやや大きめに黒く映ることがあります。
これはMRI特有のコントラストの強調によるものです。
他の撮像との違い
通常のT2強調画像やスピンエコー法では微小出血はほとんど映りません。
T2*強調画像が最も適した撮像法です。
微小出血と判断する際の目安
診断医は以下の3点を基準に評価します。
- 黒く抜けていること
- 丸または楕円形であること
- 周囲が脳実質で囲まれており、血管そのものではないこと
② 微小出血が示す“病気としての意味”
微小出血は、脳の細い血管がもろくなっているサインであり、小血管病(small vessel disease)の一部として理解されます。
分布の仕方(どこに多いか)で原因を推測することができます。
主な原因となる小血管病
1. 高血圧性小血管障害(細動脈硬化)
- 脳の深部(大脳基底核・視床・脳幹・小脳など)に多く出ます。
- 高血圧や生活習慣病と関係が強く、ラクナ梗塞や白質病変(加齢による白い変化)と併存しやすいタイプです。
2. 脳アミロイド血管症(CAA)
- 大脳皮質やそのすぐ下(皮質下)に多く出ます。
- βアミロイドが血管壁に沈着することで起こり、アルツハイマー病やAPOE遺伝型(ε2/ε4)と関係します。
臨床的な意味(どんな病気と関係があるのか)
- 脳卒中との関係:脳内出血(ICH)の方の約20~80%に微小出血が見られます。
脳梗塞を起こした方の約15~35%に見られ、特にラクナ梗塞の方では約26~62%と高率です。
微小出血が多いほど、将来の脳内出血や脳梗塞の重症化と関係します。 - 認知機能との関連:微小出血がある方は、全体的な認知機能、実行機能、注意力、思考速度が低下しやすいことが報告されています。
認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の方では、進行リスクの指標にもなる可能性があります。 - 他の画像所見との関係:非特異的白質病変やleukoaraiosis(白質変化)と並行して増える傾向があります。
- 将来のリスク予測:微小出血は、今後の脳出血や脳梗塞のリスクを予測するマーカーであると考えられています。
③ 見つかったときの対応(治療・生活で気をつけること)
微小出血は、「脳が出血するリスク」を示しているため、薬の使い方や生活習慣の見直しが大切です。
1)将来の脳内出血リスク
- 抗凝固療法中(血液をさらさらにする薬)では出血リスクが上がります。
- 脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)の既往があり微小出血がある場合、その後の脳内出血が約3倍に増えるという報告があります。
- 5個以上の微小出血があると、その後2年以内の出血リスクが上昇するとされています。
- すでに脳出血を起こした方では、再出血のリスク増加とも関連します。
2)抗血栓薬(抗血小板薬・抗凝固薬)の使い方
- これらの薬の使用は、微小出血や脳出血のリスクと関連する可能性があります。
- ただし、現時点では「微小出血があるから一律に薬を中止すべき」とまでは言えません。血栓予防の必要性と出血リスクを個別に比較して判断します。
- 代替薬の例:抗血小板薬の中でシロスタゾールはアスピリンに比べ、出血リスクを減らす可能性があるという報告があります。
3)急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法(t-PAなど)
微小出血がある方では治療後の出血リスクがやや上がる傾向がありますが、
それだけを理由に治療対象から外す根拠は不十分とされています。総合的に判断されます。
4)血圧管理の重要性
- 血圧をしっかり管理することが、最も効果的な予防策です。
- 高血圧性の出血だけでなく、アミロイド血管症による出血も減らすことができる可能性があります。
5)アルツハイマー型認知症治療との関係
- 微小出血は、抗アミロイド抗体治療(レカネマブ等)で見られる副作用である「ARIA」と関係します。
- 5個以上の微小出血がある方は、レカネマブ治療の添付文書上の禁忌に該当します。脳表ヘモジデリン沈着症または1cmを超える脳出血も同様に禁忌に該当します。
まとめ
- T2*強調画像で見つかる微小出血は、過去の小さな出血の跡です。
- これは、脳の小血管がもろくなっているサインであり、脳卒中や認知機能低下のリスクを高めることがあります。
- 血圧管理が最も重要で、抗血栓薬の使用は必要性と出血リスクを考えて個別に慎重に判断します。
- 当院では、T2*強調画像によるMRI検査と、既往・生活背景を踏まえた総合評価を行っています。
「健診で“黒い点”があると言われた」「抗血栓薬を飲んでいて不安」など、気になる方はお気軽にご相談ください。
画像と生活背景をあわせて、相反する“出血リスク”と“脳梗塞予防”のバランスを一緒に考えます。
よくあるご質問(Q&A)
微小出血があると必ず脳出血になりますか?
必ずではありません。ただし、数が多いほどリスクは上がる傾向があります。
まずは適切な血圧管理が最重要です。
アスピリンなどの「血がサラサラになる」薬は中止すべきですか?
一律には中止しません。微小出血の数・分布、脳梗塞予防の必要性、年齢や合併症などを総合的に評価し、個別に判断します。
微小出血は症状を出しますか?
多くは無症状で、過去の小さな出血の「跡」として見つかります。
ただし将来の脳卒中や認知機能低下リスクの評価に役立ちます。
微小出血は自然に消えますか?
原則として残ります。
ただし血圧管理・生活習慣の見直し・薬剤調整により、症候性出血のリスクを下げることは可能です。
どのMRIで見えますか?
T2*強調画像ではっきり見えます。通常のMRIでは見落とされる場合があります。
認知症の治療に影響しますか?
影響する場合があります。微小出血が多い(目安:5個以上)と、抗アミロイド薬の適応に制限が出ることがあります。
自分の場合はどう判断すればいいですか?
年齢・血圧・既往歴・内服薬・出血の数と場所で結論が変わります。
専門医による画像評価と相談が安心です。
受診のご案内
当院ではT2*強調画像を含む頭部MRIを用いて、脳微小出血の有無や分布を詳細に評価します。
また、血圧・内服・生活習慣を含めた総合的なリスク管理を行っています。
下高井戸脳神経外科クリニックでは条件次第で当日MRIも可能ですので、健診や他院での指摘が気になる方はお気軽にお問い合わせください。