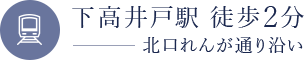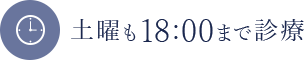慢性硬膜下血腫とは?その特徴と治療について
慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)は、脳神経外科領域で頻度の高い疾患であり、とくに高齢の方に多く発症します。社会の高齢化と抗血栓薬(血がさらさらになる薬)の使用頻度の増加に伴って、日本だけでなく世界的にその手術件数が増加しています。
発症年齢と原因:外傷性・非外傷性
慢性硬膜下血腫は、一般的に軽微な頭部外傷後に発生すると考えられています。私が脳外科医になりたての頃、先輩が「鴨居に頭をぶつけたくらいでも起こるから、慢性硬膜下血腫の原因を特定の外傷と診断するのは難しいよ」と言っていたくらいです。
外傷の病歴は症例の50〜77%で確認されていますが、患者自身が気づかないほどの軽微な外傷であることもあります。
一方、外傷によらない非外傷性の慢性硬膜下血腫もあります。非外傷性の要因としては、抗凝固薬(血をさらさらにする薬の中で血流がよどんでいる所で血栓を生じさせないための薬です)の内服などが知られています。
被膜の中で血腫が増大していく病態生理
慢性硬膜下血腫の形成は、軽微な外傷後の硬膜という脳を包む膜の辺縁にある細胞層からの出血に始まります。その後、炎症反応が活性化することで新しい被膜が形成され、血管新生因子や新しい毛細血管によって血腫が拡大していくと考えられています。
特に外膜には液体が漏れやすい未熟な毛細血管が多数存在し、これが血漿や赤血球の持続的な滲出を促し、血腫の持続的な増大に関与します。
血腫の増大と受診のタイミング
初期の外傷から臨床症状が現れるまでには、通常数週間から数ヶ月の時間がかかります。直後の画像で血腫が認められなくても、時間の経過とともに血腫が拡大し、症状が進行することが特徴です。
受傷直後の画像で硬膜下腔という脳周囲の隙間が目立つ場合は、後から慢性硬膜下血腫を生じる懸念があり、1か月程度後に再検査をすることがあります。
特徴的な症状と進行
慢性硬膜下血腫の症状は、脳が押されて生じるため、押される場所や強さによって多岐にわたります。一般的には 頭痛、歩行障害、物忘れ(認知機能障害) が代表的ですが、他にも 片半身の麻痺、めまい、不安定性、疲労、けいれん発作 などが現れることもあります。
症状が急速に進行すると、混乱、頭痛、意識レベルの低下で救急搬送されることさえあります。
私は救急外来で患者様を診察するとき、
-
歩けない患者様には何か大切な原因があるはずだ。
-
ご本人さま、ご家族さまが「いつもと違う」というときには何か大切な原因があるはずだ。
この2点を大切にしていました。実際に「数日前からよく転ぶようになって、とうとう今日動けなくなったから、悪いと思ったけれど救急でかかりました」とおっしゃる患者様もいらっしゃいました。
医療者に対するお気遣いは大変ありがたいのですが、ご不安がある際にはそこまで待たず、ぜひご相談ください。
若年者における急激な悪化のリスク
ほとんどの慢性硬膜下血腫患者は意識が清明な状態で受診されますが、一部の患者さまは重度の意識障害の状態で搬送されることもあります。
特に交通外傷やスノーボードなどのスポーツで比較的強い外力がかかった場合、若年者でも慢性硬膜下血腫を発症することがあります。そして、脳の隙間が少ない若年者に両側の血腫が生じると、急激な頭蓋内圧上昇から突然に意識障害や生命に関わる重篤な状態に陥るリスクがあります。
日々増悪する頭痛も要注意のサインです。若年〜壮年の方は我慢して仕事を続けてしまう傾向がありますが、このような場合には早めに医療機関にご相談ください。
診断方法
画像診断には一般的にCTが用いられます。CTでは血腫の形状、位置、厚さ、正中偏位、さらに発症時期による吸収値の変化(超急性期から慢性期にかけて高吸収→等吸収→低吸収へと変化)が評価されます。
MRIも診断に非常に有用であり、特に被膜の構造や血腫の組成(液体成分と固体成分の区別)、CTでは診断が難しい等吸収域の血腫描出に優れています。
当院(下高井戸脳神経外科クリニック)にはCTがありませんので、MRIで診断を行います。
治療の選択肢:手術と保存的治療
治療方針は、症状の有無と重症度、血腫のサイズ、脳の圧迫の程度によって決定されます。
-
手術適応: 神経症状がある場合、または血腫の厚さが10mm以上、正中偏位(血腫による脳のずれ)が7mm以上の場合に手術が検討されます。
-
保存的治療: 無症状の患者は、慎重な経過観察が行われることがあります。薬物療法としては、経験的に漢方薬などが使われます。エビデンスは十分ではありませんが、実際に使用すると効果を感じるケースもあります。
手術:根本的な治療とその効果
穿頭術(頭蓋骨に1か所小さな穴を開けて行う手術)は、慢性硬膜下血腫の標準的な治療法です。
-
手術手技: 局所麻酔下に頭蓋骨に穴を開け、硬膜を切開すると血腫の外膜が見えます。血腫は被膜(外膜)内に貯留していることが特徴です。血腫腔内を洗浄し、ドレナージチューブを留置する「洗浄ドレナージ」や、チューブを留置するだけの「シンプルドレナージ」が行われます。
-
治療効果: 血腫を排出することで症状が改善し、手術成績は概ね良好です。血腫が完全に排出しきれなくても量が減少すれば症状の軽快が期待できます。特に症状がある場合には、手術によって速やかに改善することが多いです。
手術後の再発と予防
慢性硬膜下血腫は手術で改善が得られることが多い病気ですが、手術後に約10%程度の患者さんで再発がみられ、再手術が必要になります。
また、頭の手術であるため、術後に脳出血や感染を合併する可能性もあります。ただし、そのまま放置することにも大きなリスクがあるため、必要な場合には慎重に手術を行います。
再発のリスク因子としては、
-
高齢で脳萎縮がある(血腫が再び溜まるスペースができやすい)
-
術前CTで血腫量が多い
-
液面形成(ニボー形成)がある
-
正中偏位が強い
といったものが挙げられます。
急速増悪のリスク:Acute on Chronic
慢性硬膜下血腫が存在する状態で再度頭部打撲を経験すると、「Acute on Chronic」と呼ばれる急性期出血が合併し、急速に症状が悪化することがあります。
そのため、慢性硬膜下血腫の経過観察中は激しい運動を控えることをおすすめしています。
再発に対する新しい治療:中硬膜動脈塞栓術(MMAE)
術後血腫の再発はまれではなく、その再発率は10%前後と報告されています。
再発を繰り返す場合や、高齢で抗凝固薬を使用しているなどの高リスク患者に対しては、中硬膜動脈塞栓術(MMAE) が有望な治療法として注目されています。
MMAEは、硬膜の血管をカテーテル治療で塞栓することで、血腫被膜の壊死や血管新生の抑制を目指します。これにより、出血や炎症性メディエーターの流入を減少させ、再発を予防する効果が期待されています。
特殊なケースでの注意点
血液疾患などで出血傾向のある患者さんの場合、慢性硬膜下血腫に見えても、実際には脳の周囲に血液が溜まっているだけで、特徴的な外膜構造を欠いていることがあります。このようなケースでは、手術による脳損傷のリスクが高まる可能性があります。
また、被膜が完全に固体の構造に変形している血腫では穿頭術で血腫を減量できないことがあり、その場合は開頭術と被膜除去が必要となることもあります。ただし、開頭術は高齢患者や凝固障害のある患者にとっては穿頭術と比べリスクが高くなります。
まとめと受診の推奨
慢性硬膜下血腫は、頭を打ってから数週間〜数ヶ月経ってから 頭痛、歩行障害、物忘れ などの症状がゆっくりと進行することが特徴です。
もし頭を打った後にこのような症状が進行するようであれば、速やかに医療機関を受診してください。
下高井戸脳神経外科クリニックでも、慢性硬膜下血腫の診断、内科的治療および経過観察に対応しております。